Tatsuya’s daily notes with his favorites of the day.
For the older posts, please check his Japanese blog called “Findings.”
Note: The RSS feed URL of Microblog has moved to https://www.tatsuyaoe.com/findings/mcbg_w/feed/
複雑系や人工生命(AL)に興味を持っていた頃、ベノワ・マンデルブロの名前と「フラクタル幾何学」という言葉を頻繁に目にした。フラクタル的なアプローチは作曲やアートの世界にも広がり、僕もその手の実験的なソフトウェアに凝った時期がある。その10年後ナシム・タレブが『ブラック・スワン』で彼を称賛したことで、マンデルブロは一躍「金融工学の人」になった。彼が現在生きていたら、現在進行中の「一人の人災による市場リスク」はどう説明するのだろう?
 ベノワ・マンデルブロ: フラクタル幾何学 (TED)
https://youtu.be/ay8OMOsf6AQ
ベノワ・マンデルブロ: フラクタル幾何学 (TED)
https://youtu.be/ay8OMOsf6AQ
複雑系や人工生命(AL)に興味を持っていた頃、ベノワ・マンデルブロの名前と「フラクタル幾何学」という言葉を頻繁に目にした。フラクタル的なアプローチは作曲やアートの世界にも広がり、僕もその手の実験的なソフトウェアに凝った時期がある。その10年後ナシム・タレブが『ブラック・スワン』で彼を称賛したことで、マンデルブロは一躍「金融工学の人」になった。彼が現在生きていたら、現在進行中の「一人の人災による市場リスク」はどう説明するのだろう?
 ベノワ・マンデルブロ: フラクタル幾何学 (TED)
https://youtu.be/ay8OMOsf6AQ
ベノワ・マンデルブロ: フラクタル幾何学 (TED)
https://youtu.be/ay8OMOsf6AQ
僕は元々寝つきが悪い上に眠りが浅くて、数時間で目が覚めることがしょっちゅうだった。燦燦と輝く太陽の下で長時間散歩してもまだビタミンDの生成量と疲れが足りないのかと思って、自然光のLEDライトとエアロバイクを部屋に導入したほど。それがこの数年なぜかぐっすり眠れていて、横になって5分で気を失う。理由ははっきりとは分からないが、床に入ると毎日儀式のようにこのアルバムをセットしている。で、悪いけど1曲目しか聴いた記憶がない(笑)。
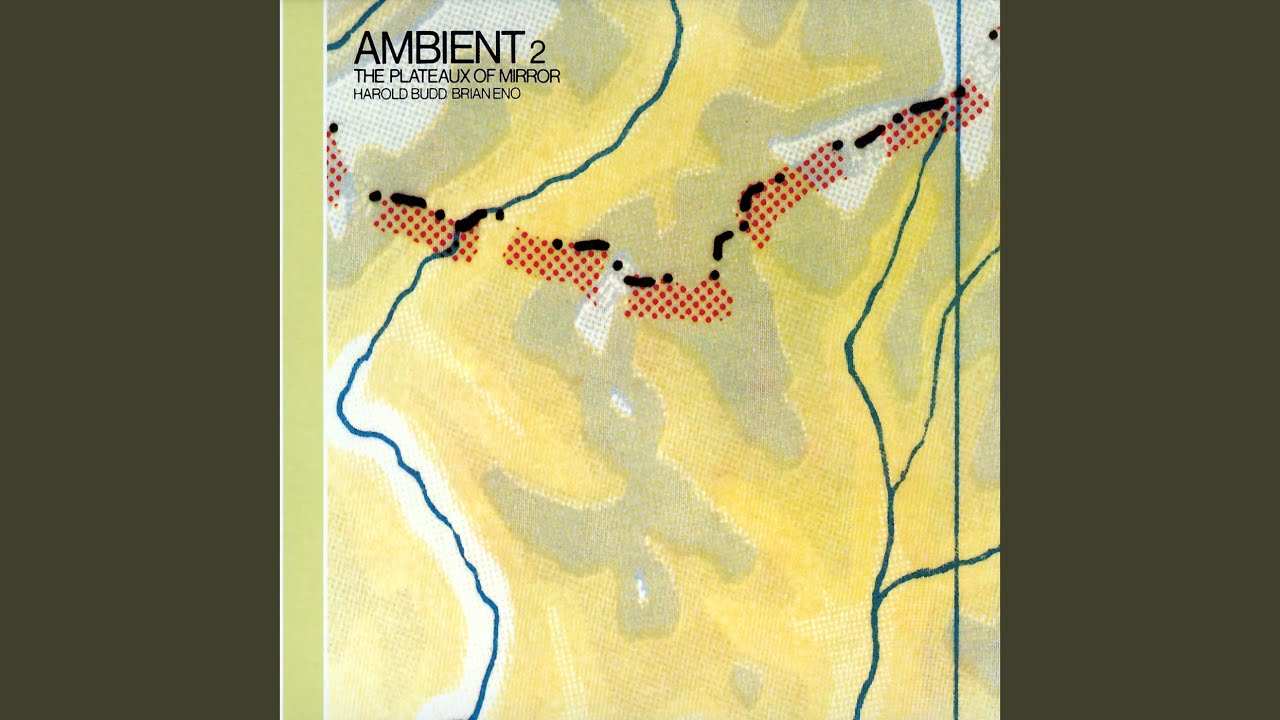 Harold Budd and Brian Eno – First Light
https://youtu.be/cOWJq88uAiQ
Harold Budd and Brian Eno – First Light
https://youtu.be/cOWJq88uAiQ
ライスの色が青い料理をご存知だろうか?マレーシアなど東南アジアにはこの青いライスを使ったカレーやナシ・クラブといったメニューがある。青は食欲を減退させる色という説もあるらしいが、僕はこの真っ青な料理を一発で気に入って、今では我が家の定番メニューに。最近気になるのは糯米鶏(ローマイガイ)というもち米を使った鶏肉料理。日本だと中華ちまきになるのだけど、鶏の中にまるごともち米を敷き詰めた、大胆な特別バージョンがあるのです。
 Recipe: Blue Coconut Rice — Lily Morello
https://www.lilymorello.com/blog/blue-coconut-rice
Recipe: Blue Coconut Rice — Lily Morello
https://www.lilymorello.com/blog/blue-coconut-rice
昨日の話の続きになるが、僕の中で”人間の創り出した「正の遺産」”の筆頭に来るものはやはり音楽。(自分にとって)良い音楽に出会うこと、また愛聴してきた音楽や自分の作った曲のメロディやアレンジがふと頭の中で流れること。こういう瞬間がある限りは、まだまだ人生にイエスと言える。ロジャー・ケラウェイのパーカッシブなピアノに乗せて歌うのは、ザ・シンガーズ・アンリミテッド。アメリカに足を踏み入れるずっと前に魅了されたアメリカ産音楽の一つ。
 The Singers Unlimited – Stone Ground Seven
https://youtu.be/RP5j8VvIBhw
The Singers Unlimited – Stone Ground Seven
https://youtu.be/RP5j8VvIBhw
僕はもともと人間が他の生き物より優れているとは思わないので、もし将来何かが起こって人類が絶滅したら、残った生命体の間で「かつて人間という愚かな動物がいたんよ、ププッ」みたいなことになるのかもな、と考える時がある。この21世紀に、文明社会が単なる「欲に群がる獣の集まり」へとグレードダウンさせられるのを目の当たりにした一週間だったが、こんなことで負けてなるものかと、人類の創り出した「正の遺産」を必死で思い出しては自らを鼓舞する日々。
 米オプションで疑惑の取引、相互関税停止発表直前で株価反発に賭け | ロイター
https://bit.ly/4cwl7Uw
米オプションで疑惑の取引、相互関税停止発表直前で株価反発に賭け | ロイター
https://bit.ly/4cwl7Uw
購読しているポッドキャストの中には、貴重な話なのにフィラー(日本語だと”えー”とか”あー”)が多かったりアクセントにクセがあって、聴き続けるのがしんどい時もある。そういう時は文字起こししたテキストを使って、読み上げアプリに読んでもらったものを録音して聴いた方がスムーズだったりする。Natural Readerのような優秀なアプリを体験すると、かつてのロボットっぽいText To Speechには戻れない。ところでこの動画のAlex君もAIでは?
 Listen Anywhere with Free AI Text-to-Speech
https://youtu.be/eGpOVq_Xed0
Listen Anywhere with Free AI Text-to-Speech
https://youtu.be/eGpOVq_Xed0
『Peak』という著書で知られる心理学者者アンダース・エリクソンは、この動画で、「パガニーニは意図的にバイオリンの弦を一本だけ残して演奏した。達人になるには、実現不可能そうな事を意図的に練習に組み込んで限界に挑む(Deliberate Practice)が大事」と説く。確かにある程度自分に負荷をかけて努力するのは成長の上で大事だと思う。ただ、星飛雄馬の「大リーグ養成ギプス」的な無茶振りは、周囲を不幸にしそうだ(笑)。
 Anders Ericsson – The myth of impossible – Insights for Entrepreneurs
https://youtu.be/2VzzriUEQFA
Anders Ericsson – The myth of impossible – Insights for Entrepreneurs
https://youtu.be/2VzzriUEQFA
日本のレアメタル事業の開拓者、中村繁夫さんの最近の映像を見た。起業した頃に彼の著作を数冊読んだことがあって感銘を受けたが、その後出家して現在は再びビジネスの現場に復帰されているらしい。バイタリティという言葉は彼のためにあるような印象すら受けるけど、それにしても彼の様な「外に出て一丁やってやるぞ!」的なメンタリティをもった大人がなぜ、そしていつの間に日本から消えてしまったのか。そこが分からない。
 資源争奪戦!世界中を飛び回る“レアメタル王”の闘い【ガイアの夜明け】
https://youtu.be/LzpGeDZNlzk
資源争奪戦!世界中を飛び回る“レアメタル王”の闘い【ガイアの夜明け】
https://youtu.be/LzpGeDZNlzk
先日音楽のテクニックについて書いたが、ウィロー・スミスのこのパフォーマンスは巧いミュージシャンを揃えないと表現できない音楽。若手の天才2人組DOMi & JD BECKの音楽辺りと同様に、かつてのエレクトロニカや音響系バンドの遺伝子が引き継がれている印象を受ける。ただ、当時の音楽にあった「どこの誰が、どうやって作ったの?」といった謎めいたワクワク期間は短く、今はすぐに「種明かし」やバックストーリーが広がってしまう。
 WILLOW: Tiny Desk Concert
https://youtu.be/DmC2QQESN6E
WILLOW: Tiny Desk Concert
https://youtu.be/DmC2QQESN6E
ピカソは「優れた芸術家は模倣し、偉大な芸術家は盗む」という自惚れ極まりない(笑)名言を残した。僕を含めて現代を生きる日本人が「盗み」や「略奪」に感じる罪悪感や非難の感情は、世界のモラル基準からするとむしろ特殊なのだと思う。国を出れば、「僕のものは僕のもの。君のものも僕のもの。」と言わんばかりの考え方の人が多いくらい。略奪世界をしなやかに生き抜くことが21世紀の必修科目。ん、近代に戻ったのか…。
 How to Create FREE Ghibli Style Images Quickly on ChatGPT? – Open AI Master
https://openaimaster.com/how-to-create-free-ghibli-sty…
How to Create FREE Ghibli Style Images Quickly on ChatGPT? – Open AI Master
https://openaimaster.com/how-to-create-free-ghibli-sty…
マンハッタンのチャイナ・タウンに売っているもので我が家の定番になったものが2つある。一つはロースト・ダックで、注文するとお店のスタッフがその場で四角い中華包丁を使い豪快にカットしてくれる。もう一つは「老干媽(ローカンマ)」というブランドのラー油。実は大型スーパーならどこでも手に入る人気商品だったのだが、もう普通のラー油には戻れないという位にお世話になった。その後ロースト・ダックからは遠ざかり、低脂肪なカオマンガイ派に。
 中華ラー油「老干媽(ローカンマ)」8種食べ比べ
https://dailyportalz.jp/kiji/laoganma-8syu-tabekurabe
中華ラー油「老干媽(ローカンマ)」8種食べ比べ
https://dailyportalz.jp/kiji/laoganma-8syu-tabekurabe
音楽はもちろん大好きだけど、YouTube等でよく話題に上る「バカテク(超絶技巧)系」のミュージシャンや動画には殆ど縁がない。テクニック自体を否定しているわけではなくて、「その音世界を形にするためにその技術が必要なのであれば」、という必然性で見ている。ただ、動画中心の文化が根付いてしまったお陰で、耳の持つ潜在的な想像力や感受性よりも、見た目のインパクトや派手さが優先されがちなことに、少し寂しさを感じる。
 Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra – Promises
https://youtu.be/Mn8x0QbN4f8
Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra – Promises
https://youtu.be/Mn8x0QbN4f8
トランプは貿易はもちろん、小売りや製造業に関する知識も、そしてそれらの業界に対する気遣いもないことは明らかだが、最近の「オウンゴール」の決めっぷりが豪快すぎる。周囲の閣僚も大半がリアリティショーに出てくる二世の不動産ブローカーみたいなメンタリティの連中だから、「海の外」の事に関してはドがつく素人だろう。英語以外話せる人はいるのだろうか?とか思ったけど、振り返れば日本の政治家も昔から、不勉強で内弁慶な二世ばかりだった。
 ポール・クルーグマン『トランプの貿易政策は狂っている』(原文)
https://paulkrugman.substack.com/p/trump-goes-crazy-on-trade
ポール・クルーグマン『トランプの貿易政策は狂っている』(原文)
https://paulkrugman.substack.com/p/trump-goes-crazy-on-trade
もち麦は食物繊維が豊富で、消化がゆっくり進むため、血糖値の急激な上昇を防ぐ効果があるという。食感も好きなので、雑穀を精白米に混ぜて炊き、食べることが習慣化している。朝は野菜と海藻(だけ)をボウル大盛りで食べる。和食は洋食よりも健康的だと言われるけど、納豆、みそ汁などは塩分が強いものも多いし、精白米は血糖値が上がりやすいなど、和食がそのままパーフェクトな訳ではない。たまに外食すると、色々気付くことがある。
 「和食は本当に健康なのか」~データで見る本当の健康とは~
https://www.videor.co.jp/digestplus/article/36157.html
「和食は本当に健康なのか」~データで見る本当の健康とは~
https://www.videor.co.jp/digestplus/article/36157.html
アメリカの労働統計局のウェブサイトには様々な職業についている人の大まかな人数と収入を紹介しているページがある。自分は”Music Directors and Composers(5万人)”か”Musicians and Singers(17万人)”に属するのかも知れないけど、僕の場合パフォーマンスもしないし他人のために作曲をするわけでもなく、仕事内容も稼ぐ方法も定義とは全然違う。どこであれ、しっくりくる居場所はないのは確か(笑)。
AIや機械学習の世界でサンプルデータの拡張/水増しをすることは常識のようになっているが、統計学的にも倫理的にも腹落ちしない場合がある。人間、つまりデータサイエンティストの主観やセンス、モラルが入る余地が大きすぎるような気がするのだ。学生ローン申請をサポートする米国のスタートアップがデータサイエンティストを雇い架空の学生400万人を捏造させたという事件は、極端な例だが上の「倫理的責任」を浮き彫りにしている。
 JPモルガンを騙したフィンテック企業の創業者に有罪判決、禁錮30年の可能性
https://forbesjapan.com/articles/detail/78165
JPモルガンを騙したフィンテック企業の創業者に有罪判決、禁錮30年の可能性
https://forbesjapan.com/articles/detail/78165


