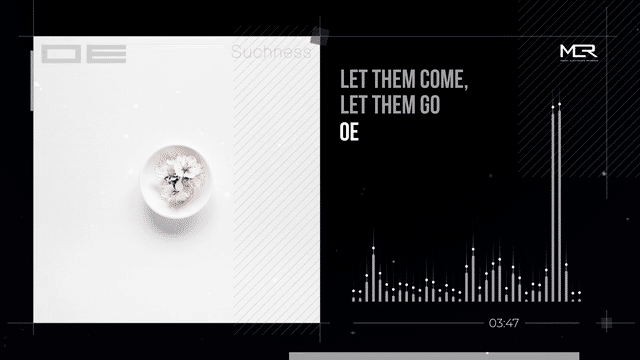Topicsのページでお伝えしたように、MER(Model Electronic Records)名義で初めての一般リリースを行います。シリーズ第6弾となる『Anti-Crime Breaks: Thrilling and Badass Jazz Funk Tracks』は、70年代のクライム・アクションやスパイ、刑事ドラマのサウンドトラックに通じる、タフでスリリングなジャズ・ファンク、ブレイクビーツ・トラックを集めています。今日はこのアルバムについての解説です。
(イントロにインパクトがあるので、ボリュームを十分に注意して聴いてください)
コンセプトの背景1:映画の原体験と、その舞台にやってきた自分
クライム・アクション・ムービーで使われる音楽は「クライム・ミュージック」とか「クライム・ジャズ」と呼ばれることがありますが、当然ながら僕は犯罪や暴力に反対なので、そこを強調するためにあえてAnti-(「アンティ」もしくは「アンタイ」「エンタイ」と読みます)を頭に付けました。
『シャフト』や『スーパーフライ』『110番街交差点』、あるいは『フレンチ・コネクション』や『サブウェイ・パニック』といった70年代のニューヨークを舞台にしたクライム・アクション映画をご存じでしょうか?僕がそれらの映画に最初に出会ったのは、今から30年以上前に東京で学生生活をしていた頃です。今思えば能天気なんですが、その当時は「えらいクールな映画と音楽を見つけた!」とばかりに、単純にエンタテインメントとして楽しんでいました。これらの映画が撮られて随分時間は経つとはいえ、その後渡米してそれらの舞台となった場所に住んでみて、僕の中でのこれらの作品の受け取り方も音楽の聴き方もその頃とは当然大きく違っていることに気付かされます。
具体的に言えば、映画である以上荒唐無稽な部分はあるにしても、マフィアと警察の抗争の歴史やレイシズムを踏まえた、「ありえそうな」光景や伏線がストーリーや映像に沢山散りばめられていることがわかるし、今の現実社会でも似たような事件やストーリーが起こりうることが想像できる。フィクションであっても、殺伐とした現実がある程度下敷きになっているのです。
それとは対照的に、子供の頃に手に汗握って見た『大都会』や『西部警察』などの日本の刑事ドラマを今見返して「やっぱりフィクション/クライム・アクション・ドラマとしてよく出来てるなー」と感心することはあっても、そこにリアリティを感じて背筋が寒くなるということはありません。僕にとってフィクションであり続けてくれるからこそ、今でも無条件で内容に没頭できるのでしょう。
コンセプトの背景2:「フィクション」が本来持つ力と行く先
ハリウッド映画での行き過ぎた暴力表現に対する批判は常にあるけれども、「映画で描かれたことは明日現実に起こりうるし、その逆も然り」なのがアメリカ。現実社会を扱うニュース番組では、「そこまで見せなくてもいいのでは?」と思うような陰惨な事件の映像を夕食時に平気でリピート放映している。そこで僕が驚かされるのは、長らく続くそういったメディア環境や現実を経て形成された、受け手の側の暴力に対するリテラシーです。「映画などで描かれるフィクションの世界もエグいが、目の前の現実も同じく暴力的で犯罪だらけのエグい社会」という、あきらめにも近い認識が大前提になっている。旧約聖書の「原罪」にも通じるこうした性悪説、絶望感がベースになっている社会というのは、儒教的な性善説に囲まれて育った我々日本人にはなかなか理解できない部分です。
1968年に表現の自主規制コード(ヘイズ・コード)が撤廃されて以降、アメリカのエンタテインメントはよりウソのない表現、リアリティを追求する方向に向かってきたと言われます。ただ、虚構の世界観やヒーローに感情移入したり、音楽で想像力をかき立てたり、圧倒的な映像美や荒唐無稽な展開で悲惨な現実を忘れてもらうことも表現者として重要な責務。たとえ犯罪を扱う映画であっても、現実社会に住む我々に活力を与えるような「良質のウソ」を創り出すエンタテインメントであって欲しいし、音楽はそれをより効果的に伝える媒介であって欲しい。
そういった「フィクションの力」を信じてクリエーションに関わっていきたいという思いで、この作品を作りました。
楽曲、プロダクションについて
次に制作面について。上述したように音楽的な着想は欧米や日本でよく見られた70年代後半のクライム・アクションやスパイ、刑事ドラマのサウンドトラックですが、それをレトロ趣味で焼き直したりフォローするのではなく、自分のキャリアにおいて手掛けてきた様々な音楽スタイルや技を駆使して、2021年現在のリスナーの皆さんが新鮮でワクワクできるようなものに仕上げたいと思いました。
ブレイク・ビーツやビッグ・ビート・スタイルを中心にしたアルバムを作ったのはCaptain Funk名義の『Bustin’ Loose(’98)』『Dancing in the Street(’99)』以来ですが、今回収録されている楽曲の方がよりジャズ・ファンク色が強く、作りも洗練されていると思います。ファーストアルバム『Encounter with…(’98)』にはジャズ寄りの曲を収録していましたが、もっと雰囲気もの的なアプローチでした。いずれにせよ、打ち込みで自作曲を作り初めて数年程度の当時の自分の知識や技術では、今の様な曲は作りたくても全く歯が立たなかったはず。
収録されている10曲の中で僕が最も好きなのは試聴で紹介した『Emergency』ですが、M1『The Fugitive』やM5『Justice City』辺りも気に入っています。どちらもブレイクビートを基調にしながら、途中ジャズの4ビートとウォーキング・ベースを取り入れたりと、起伏のある構成になっていると思います。
制作スタイルに関して言えば、AKAIのサンプラーとシーケンサー、ハードディスクレコーダーで仕上げた当時とは作り方が大きく異なり、現在は Studio OneやProtoolsなどのDAWとソフトウェア音源を使ったデスクトップ完結型のプロダクションです。当然ながら商用レコードからのサンプリングは行っておらず(この20年間一切やっていません)、全て手演奏とプログラミングによるものです。Dark Modelプロジェクトで鍛えたオーケストラ・サウンドを打ち込みで表現する技術が、今回ビッグバンド・サウンドを表現するのにも役立ってくれました。制作プロセスや使用するトラック数は昔に比べると格段に複雑で大規模ですが、ハードウェア環境はさらにミニマルになって、ギターや鍵盤などの楽器を除けば超小型PCのIntel NUC1台とディスプレイのみ。傍から見たら、恐らくこのFindingsを投稿している時の作業風景と殆ど変わらないのではないかと思います(笑)。
音楽的な内容を言葉で詳細に説明するのは野暮なので、発売日の8/23以降、是非実際に音源に触れてみて下さい。先日『Emergency』を試聴用に公開しましたが、発売日までにもう数曲公開するかも知れません。
アートワークについて
最初は70年代風のコケージャン(いわゆる「白人」ですが、この呼び方も憚られる)の刑事の写真を使ったアートワークを考えていたのですが、90年代によく見られたサブカル的なアプローチを繰り返すのはちょっとなぁと思い保留にしていました。また渡米した今となっては、実在する非アジア人の写真を僕の作品に使うことに自分でも違和感を感じていました。もっとこの作品の音のワクワクする感じ、スリリングな感じを伝える方法はないかと模索していた時に、アート・ディレクターの方から提案してもらったのが最終的に採用したアメコミ案です。アクション映画的なダイナミックさもあるし、作品のコンセプトも一目で分かる。このメリハリの効いたコマ割りが僕も気に入っています。