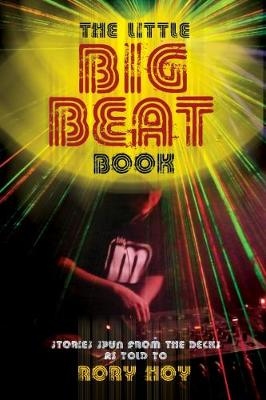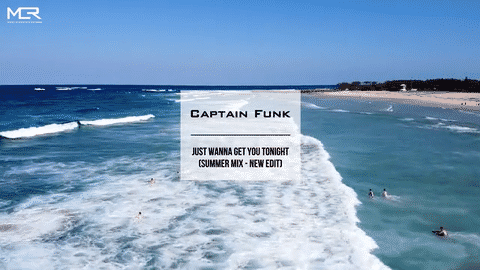Contents
新刊「The Little Big Beat Book」(英国)にインタビュー参加しました
これは恐らく世界初のビッグ・ビートに特化した書籍になるのでしょう。イギリスのDJ・ライターであるRory Hoy氏が、120人に及ぶビッグ・ビート・シーンの生き証人からのインタビューを元に、冷静な分析を交えて当時のシーンを振り返りつつ、ダンスミュージック史における今日的な意義を一冊にまとめたものです。
僕がインタビューの依頼を受けて答えたのは昨年の11月頃だったと思います。インタビューに参加した人の大部分はイギリスのミュージシャン/DJなので、僕は当時の日本のクラブ・シーンに力点を置いて答えました。ビッグ・ビートというよりも、折衷的にダンス・ミュージックを捉える、または楽しむ風潮がどのように広がっていったのか、また自分はどういった意味を見出してそのシーンに参加していったのか、その辺りを解説しています。
(10年前にこの手の依頼を受けたならば躊躇したかも知れませんが、シーンから随分離れた境遇にいる今の自分だからこそ、フラットな心持ちで取材に応じることが出来たと思います。)
今年の秋に発売になりますので、興味のある方はまず下記の出版社のリンクをチェックしてみて下さい。
Waterstones(出版社)「Little Big Beat Book」ページ(予約開始)
(追加)Amazon JP 商品ページ
僕の他にインタビューに答えたアーティスト&関係者の抜粋を紹介しておきますので、参考にして下さい。
ファットボーイ・スリム(ノーマン・クック)、ザ・プロディジー(リアム&キース)、ロバート・リネイ(ケミカル・ブラザーズ・マネージャー)、ダミアン・ハリス(Skintレコード創設者)、マーク・ジョーンズ(Wall of Soundレコード創設者)、ジョン・カーター、ベースビン・ツインズ、プロペラヘッズ、ワイズガイズ、フリースタイラーズ、ベントレー・リズム・エース、スティーブン・ホール(Junior Boys Ownレコード)、カット・ラ・ロック、ダブ・ピストルズ、ジャスティン・ロバートソン(ライオンロック)、リンディ・レイトン(ビーツ・インターナショナル)、ハウイーB、フレディ・フレッシュ、アポロ440、ミスター・スクラフ、ジョン・ゴスリング(サイキックTV、Mekon)等
「ジャンル」ではなく「アティチュード」としてのビッグ・ビート
詳しい内容は実際に本で確かめて頂くとして、当時様々な国でDJ活動を行った自分の経験から言えば、当時の日本のクラブを取り巻くシーンはイギリスを始めとする西欧のシーンの「右に倣え」ではない、日本ならではの独創的でエキサイティングなものだったと感じています。ジャンルで縦割りになりがちなクラブ・ミュージックの世界において、ハウスやインディ・ロックのファンはもちろん、ブレイク・ダンスのダンサーからバンドのミュージシャンまでがパーティーに集まるといった光景は、それまでのクラブの現場ではあまり見られませんでした。こういった音と人の両方の面で横断的な動きが見られたのは、自分の知る限り、イギリスのクラブでもごく一部だったと思います。
’97年から’01年まで行っていた自分のパーティー『Machinegun』で僕が目指していたのは、ジャンル/形式としての「ビッグ・ビート」をプレイすることではなく、クラブに限らず音楽にはびこる派閥主義やジャーナリスティックな知識・言葉偏重な傾向を乗り越え、音と人のジャンル/タイプの垣根を取り払って幅広く音楽を楽しもうという、「アティチュード」の提案、もしくは少し傲慢に聞こえるのを承知で言えば、一種の「啓蒙活動」でした。
最新のビッグ・ビートやハウス、ドラムンベースはもちろんのこと、オールド・ファンクやミドル・スクールのヒップ・ホップ、パンク・ニューウェーブ、果ては自分が手掛けた邦楽アーティストのリミックスまで、それらをランダムに(ノリ一発&ブツ切りで)スピンしていくのではなく、「ロング・ミックス」を基本にして、オーディエンスと一緒に数時間のスパンでストーリーを創り上げていく。それが「ハウス/テクノ上がり」である僕のDJとしての使命であり、パーティーを単なる「何でもあり」にしないための、死守すべきマナーだと考えていました。
形式主義、純粋主義、そしてそれらに依拠する権威主義へのレジスタンス(抵抗・反抗)を表すムーブメント用語であったはずの「ビッグ・ビート」が、次第にその反骨精神のニュアンスが薄れ、特定の形式やフォーマットを表すジャンル用語・マーケティング用語になってしまったのは否めませんが、パンクであれ、テクノであれ、ヒップ・ホップであれ、レジスタンス・ミュージックやカウンターカルチャーというのはそういう宿命を持っているものです。普及曲線のどこかの段階で形骸化・ファッション化し、その運動の根源やスピリットは風化していく。
テクノが「アンダーグラウンドに始まりアンダーグラウンドに終わる」音楽であるとすれば、ビッグ・ビートはアンダーグラウンドから既存のオーバーグラウンド・シーンに喧嘩を売りながらも、その喧嘩を自ら茶化す「やんちゃさ」を持っていたように思います。反抗心とユーモア(あるいは悪意)を行き来するトリックスター的な二面性があった。少なくとも僕はそう解釈し、そこに面白さを見出しました。
パンクやインダストリアル・ミュージックの様な階級闘争的で政治色の強いムーブメントに「いくら何でもちょっとシリアス過ぎるんじゃないの?」と辟易していたダンス好きやパーティー・ミュージック好きな連中が、もう少し肩の力が抜けたモードで、しかしあくまで「音楽本位」で、「俺たちベッドルームの手持ちの機材とネタでこんなにファンキーで楽しめる音楽作ったんだけど、どうよ?」と既存勢力に向けて笑顔でパンチを繰り出す。その音楽やパーティーが醸し出す陽気なポジティブさやユーモアにカモフラージュされてはいたものの(そのクラブらしからぬ健全な雰囲気、ロックバンドのライブの様な一体感が誤解や偏見、嫉妬(?)を呼んだのかも知れませんが)、ビッグ・ビートがある既存勢力や固定観念への挑戦であったことには変わりないと思います。
(ところで、数年前まで一世を風靡した「EDM」という言葉に違和感を持つ人が多いとすれば、この言葉とシーンにレジスタンス、カウンターカルチャー的なスピリットやロマンが感じられないからではないでしょうか。)
少し話を広げて、日・英・米の文化的土壌の違いと折衷主義について
1960年代中盤の第一次ブリティッシュ・インヴェイジョンを例に挙げるまでもなく、イギリスには、黒人音楽をはじめとした様々なルーツ・ミュージックを取り込んだ上で、英国産パッケージというオリジナル・ブランドに昇華して輸出する土壌があります。アメリカ人が人種・社会通念上の問題で足を踏み入れることに躊躇・忌避する文化的な要素を、さらりと取り入れる。ビッグ・ビートの音楽にもそういった英国産ならではの巧さ、無邪気さが感じられました。
とはいえ、折衷主義や異文化を取り入れる貪欲さや巧みさという点では、日本もそれにひけをとるものではないと考えています。イギリス以上に人種的・階級的な障壁の少ない日本だからこそ、ある時はクリエイティブに、そしてある時は節操もなく土足で他人の文化圏に入り込み、様々な要素を吸収し変容させることを得意としている。
それを良しとするかしないかの議論はさておき、その文化的土壌・習性は世界的に見ればとてつもなく稀有で、ある意味奇異なことなのです。そしてそのことは、日本の内側にいると実はあまり見えてこない部分だと感じています。
実際のところ、僕もその特異性を自分のアイデンティティと絡めて日常的に意識するようになったのは、アメリカに来てからです。DJや音楽活動を通して海外と行き来しているレベルでは、そこまではっきりと認識することはありませんでした。
「日本にいる日本人」の自分と「アメリカにいるアジア人」の自分
ヨーロッパはともかく、アメリカでは日本人であろうが韓国人であろうが、中国人であろうが、まずは「アジア人」としてまとめて認識されます。ニューヨークやカリフォルニアの一部の地域を除き、それ以上の区別に関心を持つ(親切な?)アメリカ人はあまりいないということも、日本人は知っておいても良いかと思います。
そういう環境の下で、もし僕がアメリカ生まれ、つまり「いちアジア人=マイノリティ」として生まれたとしたら、今まで自分が聴いてきた音楽の半分以上はスルーして、関心を持つことも、その良さに触れることもなかっただろうと想像することがあります。つまり、今いる自分は存在しなかっただろうと。
ヒップ・ホップは向かいに住む黒人の兄ちゃんが聴くもの、ラテン音楽はメキシカン料理屋のおっちゃんの聴くもの、パンクは隣のスケーターの悪ガキが聴くものであって、アジア人である自分が共感できる、もしくは共感を分かち合える音楽には思えなかったかも知れません。それ位、アメリカでは人種というものは自分を特徴づける強みや方便になると同時に、時に融通の利かない、足かせにもなりえます。良かれ悪しかれ、(創作活動を含め)行動一つ一つに人種というアイデンティとの紐付けや文化的な裏付けを要求される、それがこの国です。誤解を恐れず言えば、「文化的な垣根を超える」ことを必ずしも歓迎しない。そういった暗黙の了解があることを理解せずに生きてはいけません。
そういった意味でも、20年前の自分が、日本ならではの文化的土壌の中で、日本でしか生まれえないクリエイティブな環境を謳歌し、オーディエンスの皆さんと共感しあえたことはつくづく貴重な機会だったと思う次第です。