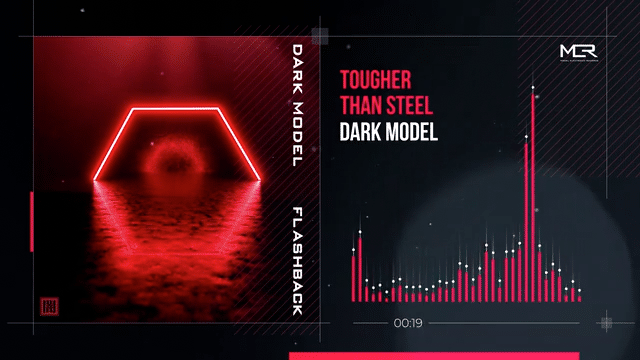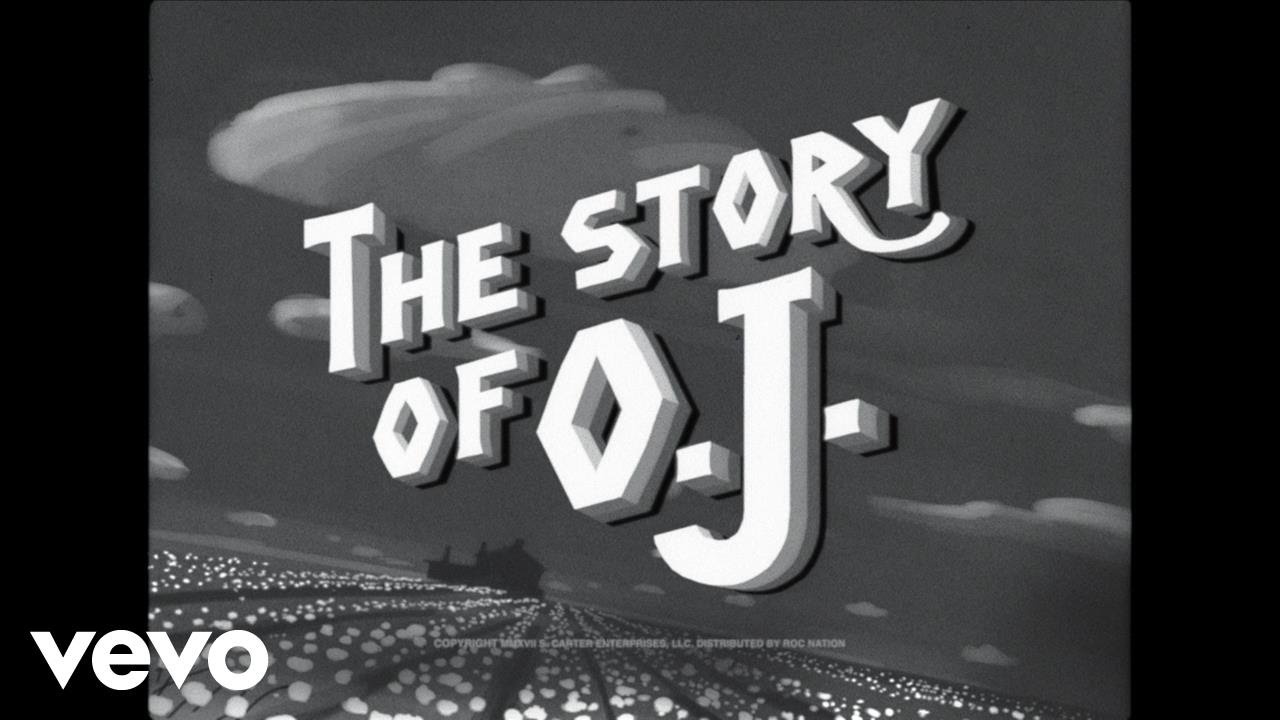Dark Model「Saga」に収録されている「Rage and Redemption」はクワイア(合唱団)とオーケストラサウンドを駆使した、インダストリアル色の強いエレクトロニック・トラックです。クワイア制作のコツ、ソフトシンセの選び方、トラック数の多い楽曲を制作するときの注意事項など、今回は音楽制作について少し具体的なお話をします。
追記(2017年4月):この投稿は、「Rage and Redemption」の最初のバージョンをYoutubeにアップした2015年8月に、Findingsに掲載したものを加筆・修正したものです。この楽曲は新たにアレンジ&ミックスされ、Dark Modelのセカンド・アルバム「Saga」に収録されています。詳細はアルバムページをご覧下さい。
また、この投稿の英語版をBlogのページにアップしました。併せてお楽しみ下さい。
Contents
「Rage and Redemption」試聴&楽曲の特徴
「Rage and Redemption」は「激情と贖罪」というタイトル通り、アグレッシヴで強いコントラストを持った曲です。ファースト・アルバムの中にも数曲クワイア/コーラル(合唱団)・サウンドを使用したものがありましたが、この曲はそれをさらに推し進めてクワイアを全面的にフィーチャーしています。Dark Modelの楽曲は質感的にトレイラーミュージックやサウンドトラック(映画音楽)と重なる部分はあるものの、この曲のようにエレクトロニックなビートを前面に打ち出したものやダンス的な要素の強いものは、そういった映画音楽周辺の音楽ではまず聴かれないと思います。皆さんにその辺りの違いを新鮮に感じて頂けたら嬉しいです。
(このYoutubeビデオはファーストバージョンです。アルバムバージョンとはミックスが異なります)
クワイア(合唱隊)・サウンドをエレクトロニックな要素とミックスする
この曲で目指したのは、ファースト・アルバムの”Ran (Resistance)“(下のビデオ)で披露したようなクワイアをフィーチャーしたエレクトロニックなサウンドの延長線上で、より躍動感を持った曲を作ることでした。僕はクワイアの中でもニューエイジ的/ヒーリング的なものではなく、もっと荘厳でクラシカルな力強いもの、出来れば狂気が感じられるものが好きなので、そういった要素を自分の引き出しやクセと照らしあわせて、いかに他にはないものを生み出すかを考えました。
この曲に着手したのは2015年の2月の初旬で、いつものように同時に何曲も並行して制作していることもあって、最終ミックスが仕上がるまでに1ヶ月半位要しました(その後「Saga」収録用に、さらにアレンジとミックスを調整しました)。使用したオーディオトラック数、MIDIトラックは合わせて数百本に上ります。
ご察しのように、一番時間がかかったのはクワイア部分です。クワイア・サウンドの制作に関してはこれも先日のドラムライン解説と同じく色々なソフトウェアや音源が巷に出回っていますが、既成のソフトウェアを音符に沿って普通に鳴らしても自分の求めている質感にはなかなか近づきません。この曲を作っている時に、僕はブルガリアにあるソフトウェア音源会社と何度か直接やり取りをして、その会社の製品の特性を最大限に引き出すコツについて色々とディスカッションしました(ついでに彼らの新製品のバグチェックにも協力しました、笑)。その会社のオーナー自身がバリトンの歌手兼作曲家なので、歌手の立場から見た苦労話も聞けて、とても有益なやり取りが出来たと思います。
これはクワイアに限らない事ですが、当然ながら鳴り方以前にハーモニー、アンサンブルとして効果的に音が配置されていないと、どんなに音源を分厚く重ねても音に説得力はなかなか出ないものです。とはいえ、こういったただでさえ沢山の要素が詰まった曲に、(バロック音楽の対位法よろしく)あまり複雑な声部の動きを盛り込んでしまうと、エレクトロニック・ミュージックとしての「勢い」「ブチ切れ感」が劇的に削がれてしまいます。その辺りを考えながら、クワイア(女声&男声)、ベース(後半は+オルガン)の動きにある程度コントラストを持たせつつ、着想した時に描いていた疾走感と荘厳さ、悲愴感のメリハリをどう演出するかを考えていきました。
適切なソフトウェア・シンセサイザー選び
クワイアの他にこの曲で力を注いだのはベース含めたシンセサイザーの音選び・音作りです。この曲のベーシックな部分はインダストリアル、ボディ・ミュージック的な質感を持っていますが、その手の音楽を象徴する硬めのベース・サウンドを作りたい場合、当然そういったアーティストが80年代、90年代に使っていたハードウェア・シンセと同じ機種を中古で手に入れるというアプローチが考えられます。しかしこれも実際に今鳴らしてみると意外と迫力が足りないことが多い。以前は僕も様々なアナログ、デジタルのヴィンテージ・ハードウェア・シンセを購入して試していましたが、現在は結果重視でソフトウェア・シンセを多用しています。僕がソフトウェア・シンセとして優れていると思うのはRob PapenとU-heという二つのメーカーです。僕は現行のハードウェア・シンセならAccessのVirusシリーズが好きですが、あのクオリティと存在感に匹敵する音源をソフトウェアに求めるのはまだまだ難しい中、上記2メーカーの製品はハードウェア含めたシンセサイザーに精通した人が作った感じが出音にしっかり込められていて、安心して使えます(Rob Papen氏の博識ぶりに関しては下の映像を参照)。どちらのメーカーも各種デモ版をダウンロードして使えると思うので、興味のある方は試してみて下さい。Rob PapenならPredator辺りから、U-heならリリースされたばかりのHiveから入るのが良いかと思います(シンセの構造に詳しい人ならZebraがお薦め)。ちなみに、僕はNative Instrumentsのプラグインを数々使いますが、シンセ関連商品に関しては残念ながら音の存在感が今ひとつなのと、他人と音が似たくないので使っていません。
ビート: コントラストと一貫性の両方を意識する
ビート周りについてはエレクトロニックなキック、スネアに加えてオーケストラ・パーカッションなどのドラマティックな音のする打楽器をアクセント的に盛り込んでいます。マーチング・ドラムやティンパニはDark Modelには既に欠かせないアンサンブル要員になっていますね。前半は少しトライバルなビート、後半はダブステップ的なビート・パターンにしてグルーヴのコントラストをつけていますが、どちらのパートも同じドラムキットを使って、サウンドとしてちぐはぐな鳴り方をしないように打ち込んでいます。4つ打ちとダブステップ的なビートパターンを交互する曲というのはよくありますが、ビートが変化した途端に失速し、間延びした感じにならないためには、前後のハットのリズムパターン、特に16分音符の使い方を工夫することが大事かと思います。ミニマル・テクノが好きな人ならハットの微妙な変化だけで狂喜乱舞できるはずですが(笑)、他のエレクトロニック・ミュージックにおいてはハットのプログラミングは結構おざなりにされることが多い、実は「盲点」のパートだと思います。
木を見過ぎず森を見る。「客観性」の罠にはまって大胆さを失わないこと。
とはいえ、ビートだけではなくメロディやハーモニー、生楽器のアンサンブルなど沢山の要素が入ってくる楽曲の場合、あまりミクロ的・局地的な視点でプログラミング&作曲していると、全体としての輪郭や音楽的な説得力・本質が失われてしまうことがあります(なので僕はあまり技術的な詳細や機材の話「だけ」に終始しないようにしています)。そこを乗り越えるために「着目する部分を日毎に変える」とか「別の再生環境で聴いてみる」とかして、自分の制作や進行確認のパターンに変化をつけることも大事でしょう。細部にこだわった作業をする場合は、「作り手と聴き手は聴いている部分が違う」という現実を忘れず、「一番聴いてもらいたい部分は何か」を常に点検しながら制作を進めるのが良いかと思います。
クリエイターは自分なりにどんなにこだわる部分があっても、「そんなの誰も気にしてないよ」と自分を突き放す姿勢は忘れないようにしたいところ。ただし「客観性」という幻想の産物(魔物でもいいです)に取り憑かれて、自分を小さくまとめてしまわないようにしたいものです。客観的になることで傑作を生み出した人なんていません。自分本来の大胆さを失わないようにしましょう。途中どんな意見に耳を傾けようが、あなたが自分の名前を刻んで生み出したものに最後まで付き合える(=責任を背負う)のはあなた自身だけなのですから。